年金について横断的に書かれたものがなく難解だったので、なるべく簡単にまとめてみました。
後半は、年金受給と仮に年金を支払わなかった場合の簡易シミュレーションをしています。
年金肯定派、年金否定派、年金崩壊?払い損?
一緒に考えてみましょう。
まえがき
会社から、拠出型企業年金保険がなんたら、と連絡が来て、最近読んだFP3級の本で詳細を調べてみました。
そしたら、なんと記載がないんです!!!
なぜなら、拠出型企業年金”保険”は年金ではなくいわば年金タイプの”保険”だったのです。
後述する、企業型確定拠出年金と勘違いしていました・・・
この際、紛らわしい年金名称とその他もろもろの制度について、整理して共有しようと思ったのが始まりです。
なお、この記事の著者のびたは経済など素人であるため、間違いもあるかと思いますがご容赦願います。
年金の種類と内容
以下は、主にサラリーマン向けの年金(と保険)です。
自営業等向けには、国民年金基金(これもまた名称が紛らわしい)もあります。
国民年金(公的年金その1、別名:老齢基礎年金)
| 対象 | 自営業、学生、無職、サラリーマン、公務員など (強制) |
| 保険料負担者 | 受給者本人 |
| 保険料 | 17,510円/月 (一律) |
| 手数料 | なし |
| 掛け金に対しての課税 | 0% |
| 運用に対しての課税 | 0% |
| 受給額に対しての課税 | (年金額-各種控除)×5.105% |
| 受給資格 | 納付期間が120月以上 |
| 受給期間 | 存命期間中 |
| 運用 | 独立行政法人 GPIF |
| メリット | 保険料が全額控除(払った分は課税対象外) 障がい者年金、遺族年金が必要に応じて支給 |
| デメリット | 60歳を過ぎないと受給できない 少子高齢化により受給額が減る可能性 |
| コメント | 投資をやっている人なら課税の小ささに目が行くかと思います。 一般的に株などは利益に対して20%の税金が徴収されます。(NISAは0%) 税制面に関して言えば相当優遇されているのがわかるかと思います。 |
厚生年金(公的年金その2)
| 対象 | サラリーマン、公務員 (強制) |
| 保険料負担者 | 受給者本人と会社が半分ずつ負担する |
| 保険料 | 標準月額報酬に対して18.3% (18.3%を半分ずつ負担する) 標準月額報酬:4,5,6月の平均給与 |
| 手数料 | なし |
| 掛け金に対しての課税 | 0% |
| 運用に対しての課税 | 0% |
| 受給額に対しての課税 | (年金額-各種控除)×5.105% |
| 受給資格 | 納付期間が120月以上 |
| 受給期間 | 存命期間中 |
| 運用 | 独立行政法人 GPIF |
| メリット | 保険料が全額控除(払った分は課税対象外) 障がい者年金、遺族年金が必要に応じて支給 |
| デメリット | 60歳を過ぎないと受給できない 少子高齢化により受給額が減る可能性 |
| コメント | 特徴は国民年金と同じですね。 厚生年金の特徴は、給与に比例して負担金(=将来の受給額)が増えるということです。 |
個人型確定拠出年金(iDeCo、確定拠出=支払い額一定)
| 対象 | 自営業、サラリーマン、公務員など (任意) |
| 保険料負担者 | 受給者本人 |
| 保険料 | 自由、ただし上限あり |
| 手数料 | あり |
| 掛け金に対しての課税 | 0% |
| 運用に対しての課税 | 0% |
| 受給額に対しての課税 | あり、ただし公的年金等控除適用 |
| 受給資格 | 納付期間が120月以上 |
| 受給期間 | 年金としては5年以上20年以下、一括受給も可 |
| 運用 | 運用会社の商品から自分で選択 |
| メリット | 掛け金と運用が非課税、受け取り方法が選べる 障がい者年金、死亡時一時金が必要に応じて支給されるものもある |
| デメリット | 60歳を過ぎないと受給できない 運用方法によっては元本割れを起こす |
| コメント | これは任意の年金ですね。 これも税制面で優遇されていますね。 |
企業型確定拠出年金(確定拠出=支払い額一定、別名:企業型DC)
| 対象 | 自営業、サラリーマン、公務員など (会社によって強制) |
| 保険料負担者 | 会社(+受給者本人も可能) |
| 保険料 | 上限あり |
| 手数料 | 不明(会社負担?) |
| 掛け金に対しての課税 | - |
| 運用に対しての課税 | 0% |
| 受給額に対しての課税 | あり、ただし公的年金等控除適用 |
| 受給資格 | 1月から |
| 受給期間 | 年金としては5年以上20年以下、一括受給も可 転職時等で、脱退一時金あり |
| 運用 | 運用会社の商品から自分で選択 |
| メリット | 運用が非課税、受け取り方法が選べる 障がい者年金、死亡時一時金が必要に応じて支給されるものもある |
| デメリット | 60歳を過ぎないと受給できない 運用方法によっては元本割れを起こす |
| コメント | これはなにかというと、退職金の代わりですね。 普通の退職金は、会社が全部面倒見てくれますが、こちらは運用は自己責任で自由にやってね。 というものです。 |
確定給付型企業年金(確定給付=給付額一定、別名:企業型DB)
| 対象 | 自営業、サラリーマン、公務員など (会社によって強制) |
| 保険料負担者 | 会社(+受給者本人も可能) |
| 保険料 | 上限あり |
| 手数料 | 不明(会社負担?) |
| 掛け金に対しての課税 | - |
| 運用に対しての課税 | 0% |
| 受給額に対しての課税 | 7.6575% 一律 |
| 受給資格 | 1月から |
| 受給期間 | 年金としては5年以上20年以下、一括受給も可 |
| 運用 | 運用会社の商品から自分で選択 |
| メリット | 受給額が一定 運用が非課税、受け取り方法が選べる 障がい者年金、死亡時一時金が必要に応じて支給されるものもある |
| デメリット | 60歳を過ぎないと受給できない 場合によっては確定申告の必要あり |
| コメント | こちらは給付額一定の退職金代わりの年金ですね。 |
【参考】拠出型企業年金保険(≠年金、年金タイプの保険商品)
| 対象 | サラリーマン、公務員など (保険会社との契約による) |
| 保険料負担者 | 受給者本人 |
| 保険料 | 自由、上限あり |
| 手数料 | 不明 |
| 掛け金に対しての課税 | 保険料控除の適用可能 |
| 運用に対しての課税 | 運用会社負担 |
| 受給額に対しての課税 | 年金年額-必要経費が25万円以上だと10.21% |
| 受給資格 | 1月から |
| 受給期間 | 保険会社による |
| 運用 | 保険会社 |
| メリット | いつでも現金化ができる 税制面で一部優遇されている |
| デメリット | 加入してから数年たたないで脱退した場合は確実に元本割れを起こす 年金に比べて税制優遇が少ない |
| コメント | 年金とは別物です。 年金と違っていつでも現金化できるのが非常に大きい。 個人的な感覚としては、積み立て貯金の上位版です。 保険料控除で住民税等も減らせるし、貯金に比べて利息も高い。 私は、拠出型企業年金保険を企業型確定拠出年金と勘違いしていました。 |
【参考】株式投資(NISA含む)
| 対象 | 全員 |
| 負担者 | 全員 |
| 投資額(保険料) | 投資額による |
| 手数料 | 基本なし |
| 元金(掛け金)に対しての課税 | 総支給額から所得税、住民税、社会保険料を差し引かれた額 |
| 運用に対しての課税 | 20.315%(NISA枠内に限り無料) |
| 利益(受給額)に対しての課税 | 20.315%(NISA枠で投資したものに限り無料) |
| 受給資格 | - |
| (受給)期間 | NISA枠は1年で復活 ただし、トータルでの限度額はあり |
| 運用 | 全額負担者 |
| メリット | 流動性が高い。(いつでも現金化できる) |
| デメリット | 勉強が必要 |
| コメント | NISA枠を超えた運用をしようとすると税率が非常に高い。 比較的ハイリスク・ハイリターン いかにリスクを抑えるかが投機と投資の違いだと思う。 元金で各種税と保険料が差し引かれているのも痛手。 |
まとめ
年金に共通すること
メリット
・税金面の優遇が大きい
・もしものとき、具体的には障がい者や死亡時の保証が手厚い
・公的年金は存命中はずっと受給できる。
デメリット
・60歳にならないと受給できない。
コメント
税金が払い損とかも聞くけど、受給額よりも障がい者年金と遺族年金の存在のほうが大きいと思う。
払い損というのも、年金として支払わなかった場合に、住民税等で引かれることを考えたらどっちが手元に残るのかは疑問。
この疑問に対しては、簡単なシミュレーションをしてみようと思う。
年金は払い損になるのか?簡易シミュレーションをしてみた。
年金が破綻する、とか、払い損になる、といったことはよく聞きます。
しかしながら、非常にふわっとしたことしか言わないので簡単にシミュレーションしてみました。
要点としては、控除が大きい年金に対して、年金支払い分を自力で運用した場合にどうなるか、です。
条件とシミュレーションの内容
サラリーマンを想定して22歳から60歳までの期間加入する。
大卒男性の平均生涯年収2億7千万円を使用する。
受給期間は65歳から、平均寿命の81歳までとする。
年金加入者は、国民年金と厚生年金の2つに加入しているとする。
流れは以下の通り。
1.22歳時の年収を500万円として、年収が一定値で増加し、平均生涯年収と帳尻が合うように計算する。なお、ボーナスを加味して年収は16か月分とし、平均月額報酬を計算する。
2.平均月額報酬から厚生年金保険料を算出する。
3.年金非加入者は、総支給額に対して年金以外の全額住民税等がかかるとする。
4.1年ごとに計算して、金額差を求める。
5ー1.年金加入者と、年金非加入者が投資をしなかった場合に、等しくなる点を求める。
5-2.年金加入者と、年金非加入者が投資をした場合に、81歳時点で同じ所得になる場合の利回りを計算する。
6.まとめ
平均月額報酬の計算
22歳から60歳の38年間で、生涯年収26,000万円。22歳の年収は500万円。とすると
60歳の年収Aは
A=26,000/38×2-500=921万円
年収についてまとめると、22歳で年収500万円、60歳で年収921万円。
毎年の年収の増加値をみていく。
(921-500)/38=11万円
これらの値を計算の便宜上、
22歳の年収は500万円、毎年の年収の増加値を10万円、とすると
60歳の年収は880万円となり、生涯年収は26,910万円となる。
平均生涯年収の27,000万円と比較するとそれなりに近い値となることが確認できた。
よって、22歳の年収を500万円とし、年収は毎年10万円ずつ増加するものとする。
なお、標準月額報酬は、年収を16か月で割った値とした。
考慮した税金や控除など
年金:国民年金、厚生年金
控除:基礎控除、給与所得控除、国民年金・厚生年金に係る控除
税金:住民税、所得税、資産運用によって生じた雑所得に係る税、年金受給に係る税
資産運用によって生じた利回りは年3%として、0.2%の税率とした。
資産運用は、
年金非加入者の年収-年金加入者の年収を投資に回す金額とした。
結果
表1.年金加入者と非加入者の生涯収入
| 年齢[歳] | 年金加入者の総収入 [万円] | 年金非加入者の総収入 [万円] | 年金非加入者が投資した 場合の総収入[万円] | 加入者-非加入者の 総収入[万円] | 加入者-投資した場合の 非加入者の総収入[万円] |
| 60 | 21189 | 23096 | 23771 | -1907 | -2582 |
| 71 | 23213 | 23096 | 27163 | 117 | -3950 |
| 81 | 26104 | 23096 | 28302 | 3008 | -2198 |
表2.年金の控除による節税効果
| 総手取りに年金支払い総額を 加算した値[万円] | 年金非加入者の総手取り[万円] | 差額[万円] |
| 23855 | 23096 | 759 |
結論
年金非加入者の総収入は、71歳の時点で年金加入者と逆転する。
また、年金非加入者が手取りの差額を年3%の利回りの投資をした場合、平均寿命時に年金加入者に比べて2198万円所得が増加している。
仮に、年金の支給額が支払った額しかもらえなかった場合は、年金の徴収に比べて759万円分の差額が生じる。
つまりは年金に加入するだけで759万円分お得、節税できる。
これは年金の支払い時に所得控除が受けられる点と、手取りが多くなった分所得税が高くなったためである。
所感
今回は、仮に年金加入が自由、もしくは年金が破綻した場合を想定して空想的なシミュレーションを行った。
実際には、2つの年金は強制である。
また、年金は税制面で有利なこと以外にも障がい者年金と遺族年金が必要に応じて給付されるということは見落としがちである。
この点は、年金を考えるうえで非常に重要だと思う。
強制加入の公的年金以外の年金は受給年齢に達するまで受給ができないことと将来のライフプランをしっかりと考えて加入することが肝要だと感じた。
そういう点では、拠出型企業年金保険は途中脱退もできるので金利のいい積み立て貯金と考えれば良い商品とも感じた。
長文をお読みいただきありがとうございました!間違いがあったらごめんね!
筆者について
筆者 のびた
3DPなどを使って創作活動をしています。
BASEで販売をしています。
ツイッターはこちら

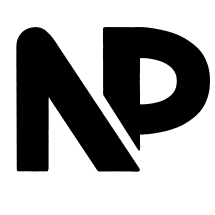

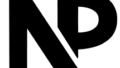

コメント